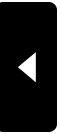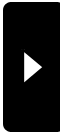2010年09月23日
十五夜
天気予報ではお月さまが顔を出してくれる確率は低い。と言うことでしたが
今もまんまるお月さんの顔が見えます


十五夜
旧暦の8月15日、新暦では9月の中旬(2010年は9月22日)。お月見、名月、中秋の名月、芋名月とも呼ばれます。
中国では、唐の時代から中秋の名月を鑑賞する風習があったようです。
日本では平安時代の貴族の間に取り入れられ、次第に武士や町民に広まりました。
昔は、月の満ち欠けにより月日を知り、農事を行いました。十五夜の満月の夜は祭儀の行われる大切な節目でもあったようです。
満月に見立てたお団子と魔除けの力があるといわれるすすきをお供えします。
日本では昔から、同じ場所で十五夜と十三夜の両方を観賞する風習が一般的です。
どちらか一方だけ観賞するのは「片見月」といって忌まれていたからです。
今は、十三夜は十五夜に比べてあまり一般的でないようで、十三夜の頃に月見団子を販売していない和菓子屋さんもあるようです。
でも、両方の月を愛でるのは、日本独特の風情ある風習ですから、ぜひどちらの月も楽しんでみてください。
※旧暦の8月15日を「中秋の名月」と呼びますので、必ずしも満月の日とは限りません。
2010年は9月22日が「十五夜・中秋の名月」。満月は9月23日です。
中秋の名月
年に12~13回の満月があるのに、どうして中秋の名月は特別な日とされているのでしょうか。
中秋の時季は、春や夏に比べると空気が乾燥し、月が鮮やかに見えるからです。
冬の月はさらに鮮やかに見えますが、寒すぎて鑑賞するには不向きだからでしょう。
月待ち
十三夜・十五夜・十七夜・二十三夜など、特定の月齢の日に、月の出を待つしきたりがありました。
たくさんの人が集まって、お供え物をし月の出るのを待ち、月を拝んで、飲食を共にします。
二十三夜の月待ちが最も多く行われていたようです。
「日本の行事・暦」より ↓
http://koyomigyouji.hp.infoseek.co.jp/index.html
 byチェリー号船長の釣り日記
byチェリー号船長の釣り日記
今もまんまるお月さんの顔が見えます



十五夜
旧暦の8月15日、新暦では9月の中旬(2010年は9月22日)。お月見、名月、中秋の名月、芋名月とも呼ばれます。
中国では、唐の時代から中秋の名月を鑑賞する風習があったようです。
日本では平安時代の貴族の間に取り入れられ、次第に武士や町民に広まりました。
昔は、月の満ち欠けにより月日を知り、農事を行いました。十五夜の満月の夜は祭儀の行われる大切な節目でもあったようです。
満月に見立てたお団子と魔除けの力があるといわれるすすきをお供えします。
日本では昔から、同じ場所で十五夜と十三夜の両方を観賞する風習が一般的です。
どちらか一方だけ観賞するのは「片見月」といって忌まれていたからです。
今は、十三夜は十五夜に比べてあまり一般的でないようで、十三夜の頃に月見団子を販売していない和菓子屋さんもあるようです。
でも、両方の月を愛でるのは、日本独特の風情ある風習ですから、ぜひどちらの月も楽しんでみてください。
※旧暦の8月15日を「中秋の名月」と呼びますので、必ずしも満月の日とは限りません。
2010年は9月22日が「十五夜・中秋の名月」。満月は9月23日です。
中秋の名月
年に12~13回の満月があるのに、どうして中秋の名月は特別な日とされているのでしょうか。
中秋の時季は、春や夏に比べると空気が乾燥し、月が鮮やかに見えるからです。
冬の月はさらに鮮やかに見えますが、寒すぎて鑑賞するには不向きだからでしょう。
月待ち
十三夜・十五夜・十七夜・二十三夜など、特定の月齢の日に、月の出を待つしきたりがありました。
たくさんの人が集まって、お供え物をし月の出るのを待ち、月を拝んで、飲食を共にします。
二十三夜の月待ちが最も多く行われていたようです。
「日本の行事・暦」より ↓
http://koyomigyouji.hp.infoseek.co.jp/index.html
 byチェリー号船長の釣り日記
byチェリー号船長の釣り日記
Posted by チェリー号船頭 at 00:11│Comments(0)
│船頭の酔いどれ日記




 お魚おもしろ話
お魚おもしろ話