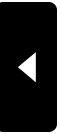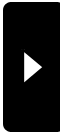2009年10月16日
セイタカアワダチソウ(背高泡立草)
セイタカアワダチソウ

名古屋市中川区「あおなみ線」小本駅南付近で



提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
セイタカアワダチソウ(背高泡立草)は、キク科アキノキリンソウ属の多年草。
北アメリカ原産で、日本では切り花用の観賞植物として導入された帰化植物(外来種)であり、ススキなどの在来種と競合する。
河原や空き地などに群生し、高さは1-2.5m、良く肥えた土地では3.5mくらいにもなる。
茎は、下の方ではほとんど枝分かれがなく、先の方で花を付ける枝を多数出す。
花期は秋で、濃黄色の小さな花を多く付ける。種子だけでなく地下茎でも増える。アレロパシーを有する。
よくブタクサと間違われるが、別の植物である。
日本国内への移入は、明治時代末期に園芸目的で持ち込まれ、「昭和の初めには既に帰化が知られている」
との記述が牧野日本植物図鑑にある。
その存在が目立つようになったのは第二次世界大戦後で、アメリカ軍の輸入物資に付いていた種子によるもの、
養蜂家が蜜源植物として利用するため、等が拡大起因とされており、昭和40年代以降には全国、
北海道では比較的少ないが関東以西から九州にて特に大繁殖するようになった。
沖縄県へも侵入しているが、沖縄本島や久米島などの一部地域で小規模な繁茂に留まっている。
昭和40年代の繁殖状況は、アレロパシー効果でススキ等その土地に生息していた植物を駆逐し、
モグラやネズミが長年生息している領域で肥料となる成分が多量蓄積していた地下約50cmの深さまで根を伸ばす生態であったので、
そこにある養分を多量取り込んだ結果背が高くなり、平屋の民家が押しつぶされそうに見えるほどの勢いがあった。
しかし、平成に入る頃には、その領域に生息していたモグラやネズミが駆除されてきたことによって希少化し
土壌に肥料成分が蓄えられなくなり、また蓄積されていた肥料成分を大方使ってしまったこと、
他の植物が衰退してしまったことで自らがアレロパシー成分の影響を強く受けてしまったこと等の理由により、
派手な繁殖が少なくなりつつあり、それほど背の高くないものが多くなっている。
セイタカアワダチソウの勢いが衰えてきた土地にはススキなどの植物が再び勢力を取り戻しつつある。
花言葉 生命力

名古屋市中川区「あおなみ線」小本駅南付近で



提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
セイタカアワダチソウ(背高泡立草)は、キク科アキノキリンソウ属の多年草。
北アメリカ原産で、日本では切り花用の観賞植物として導入された帰化植物(外来種)であり、ススキなどの在来種と競合する。
河原や空き地などに群生し、高さは1-2.5m、良く肥えた土地では3.5mくらいにもなる。
茎は、下の方ではほとんど枝分かれがなく、先の方で花を付ける枝を多数出す。
花期は秋で、濃黄色の小さな花を多く付ける。種子だけでなく地下茎でも増える。アレロパシーを有する。
よくブタクサと間違われるが、別の植物である。
日本国内への移入は、明治時代末期に園芸目的で持ち込まれ、「昭和の初めには既に帰化が知られている」
との記述が牧野日本植物図鑑にある。
その存在が目立つようになったのは第二次世界大戦後で、アメリカ軍の輸入物資に付いていた種子によるもの、
養蜂家が蜜源植物として利用するため、等が拡大起因とされており、昭和40年代以降には全国、
北海道では比較的少ないが関東以西から九州にて特に大繁殖するようになった。
沖縄県へも侵入しているが、沖縄本島や久米島などの一部地域で小規模な繁茂に留まっている。
昭和40年代の繁殖状況は、アレロパシー効果でススキ等その土地に生息していた植物を駆逐し、
モグラやネズミが長年生息している領域で肥料となる成分が多量蓄積していた地下約50cmの深さまで根を伸ばす生態であったので、
そこにある養分を多量取り込んだ結果背が高くなり、平屋の民家が押しつぶされそうに見えるほどの勢いがあった。
しかし、平成に入る頃には、その領域に生息していたモグラやネズミが駆除されてきたことによって希少化し
土壌に肥料成分が蓄えられなくなり、また蓄積されていた肥料成分を大方使ってしまったこと、
他の植物が衰退してしまったことで自らがアレロパシー成分の影響を強く受けてしまったこと等の理由により、
派手な繁殖が少なくなりつつあり、それほど背の高くないものが多くなっている。
セイタカアワダチソウの勢いが衰えてきた土地にはススキなどの植物が再び勢力を取り戻しつつある。
花言葉 生命力
Posted by チェリー号船頭 at 00:05│Comments(0)
│花









 お魚おもしろ話
お魚おもしろ話