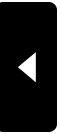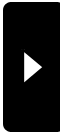2011年12月13日
ブロッコリー・カリフラワー
ブロッコリー
名古屋市中川区西前田町で


カリフラワー
名古屋市中川区野田町で


byチェリー号船長の釣り日記
名古屋市中川区西前田町で



カリフラワー
名古屋市中川区野田町で



byチェリー号船長の釣り日記
ブロッコリーは、アブラナ科の緑黄色野菜。キャベツの変種。和名はミドリハナヤサイ(緑花椰菜)、メハナヤサイ(芽花椰菜)。
ブロッコリーはカリフラワーの変種で、カリフラワーの方が人類に栽培される以前の原種に近い植物である。単位は「株」である。
地中海沿岸の原産。
食用とするのは蕾の状態の花序と茎であり、収穫せずに栽培を続けると巨大になった花序に多数の黄色やクリーム色の花をつける。
品種はピクセル、エンデバー、グリーンベール、シャスター、パラグリーン、マーシャル、チャレンジャー、
海嶺、雷鳴、緑炎、緑帝、緑笛、緑嶺などがある。
日本での主産地は埼玉県(2004年収穫量:14,000t、栽培面積:1,110ha)、愛知県(同:11,700t、825ha)、
北海道(同:10,800t、1,250ha)であり、市町村別では愛知県の田原市が全国で最も生産量が高い。
緑色の花蕾と茎を食用とする。ビタミンB、ビタミンC、カロチンや鉄分を豊富に含む。
日本ではゆでてマヨネーズなどの調味料をつけて食べることが多いが、欧米ではサラダなどで生食されることも少なくない。
スープやシチューの具、炒め物、天ぷらにすることもある。茎の部分の外皮は、繊維質で硬く食感が悪いことがあり、
その場合は剥いてから調理するとよい。
保存温度は低いほうがよく、野菜室程度の温度では花蕾が育ち花が咲くこともある。そうなると味と食感が落ちるが、食用は可能である。
また、発芽したての子葉と胚軸を、カイワレダイコン同様スプラウト(もやし)として食用にする。
一般には、ブロッコリースプラウトと呼ばれる。
カリフラワーはアブラナ科アブラナ属の一年生植物。頂花蕾を食用にする淡色野菜として栽培されるほか、観賞用途でも利用される。
名前の由来はキャベツ類の花を意味する。和名はハナヤサイ(花椰菜)、ハナカンラン(花甘藍)。
木立花葉牡丹(キダチハナハボタン)、花キャベツと呼ぶこともある。
白くこんもりとした花蕾と太い茎が特徴。 よく似たブロッコリーは別変種。
カリフラワーの原産地については未だ明白になっていない。
地中海沿岸原産のケールなど栽培されていた野菜から、突然変異によって生まれた、あるいは近東を原産地とするものが、
ローマ帝国の衰退後にアラブ人の手によってヨーロッパに伝えられた、などと言われている。
ケールなどで開花前の蕾を食用にすることは古代から行われ、紀元前540年頃の記録にも残っている。
これは現在の食用菜の花(はなな)やカイランと同様で、今日見られるようなカリフラワーは、
この用途に適した変異種が選抜されたものと考えられる。
花蕾の断面15世紀にイタリア、フランスで栽培されはじめ、16世紀になるとヨーロッパ全体に広まり、品種改良も進んだとみられる。
18世紀頃にはインドで熱帯でも栽培できる品種が開発された。
日本では白(クリーム色)の花蕾以外ほとんど生産されていないが、オレンジ・紫等の花蕾を付ける品種もあり、カラフルである。
茎の肥大化と花蕾(からい)が発育しない性質により、花梗(かこう)は低い位置で球状の塊となる。
収穫せず生育させても、他のアブラナ属のようには伸長しない。
日本でも最近認識されてきた緑色のロマネスコ品種名「カリブロ」等も仲間である。
太い茎がミネラル・ビタミンを貯蔵する器官としての役割を果たすため、良質な花や実がつき、他のアブラナ科植物より栄養価が高い。
日本には明治初期に渡来。花梛菜(はなはぼたん)、英名カウリフラワーと紹介され試作されたが、
食用としても観賞用としても普及しなかった。
第二次世界大戦後に進駐軍向けに栽培が行われ、日本での洋食文化の広まりと、改良種の輸入、
栽培技術の進歩により昭和30年頃から広く普及した。
 byチェリー号船長の釣り日記
byチェリー号船長の釣り日記
ブロッコリーはカリフラワーの変種で、カリフラワーの方が人類に栽培される以前の原種に近い植物である。単位は「株」である。
地中海沿岸の原産。
食用とするのは蕾の状態の花序と茎であり、収穫せずに栽培を続けると巨大になった花序に多数の黄色やクリーム色の花をつける。
品種はピクセル、エンデバー、グリーンベール、シャスター、パラグリーン、マーシャル、チャレンジャー、
海嶺、雷鳴、緑炎、緑帝、緑笛、緑嶺などがある。
日本での主産地は埼玉県(2004年収穫量:14,000t、栽培面積:1,110ha)、愛知県(同:11,700t、825ha)、
北海道(同:10,800t、1,250ha)であり、市町村別では愛知県の田原市が全国で最も生産量が高い。
緑色の花蕾と茎を食用とする。ビタミンB、ビタミンC、カロチンや鉄分を豊富に含む。
日本ではゆでてマヨネーズなどの調味料をつけて食べることが多いが、欧米ではサラダなどで生食されることも少なくない。
スープやシチューの具、炒め物、天ぷらにすることもある。茎の部分の外皮は、繊維質で硬く食感が悪いことがあり、
その場合は剥いてから調理するとよい。
保存温度は低いほうがよく、野菜室程度の温度では花蕾が育ち花が咲くこともある。そうなると味と食感が落ちるが、食用は可能である。
また、発芽したての子葉と胚軸を、カイワレダイコン同様スプラウト(もやし)として食用にする。
一般には、ブロッコリースプラウトと呼ばれる。
カリフラワーはアブラナ科アブラナ属の一年生植物。頂花蕾を食用にする淡色野菜として栽培されるほか、観賞用途でも利用される。
名前の由来はキャベツ類の花を意味する。和名はハナヤサイ(花椰菜)、ハナカンラン(花甘藍)。
木立花葉牡丹(キダチハナハボタン)、花キャベツと呼ぶこともある。
白くこんもりとした花蕾と太い茎が特徴。 よく似たブロッコリーは別変種。
カリフラワーの原産地については未だ明白になっていない。
地中海沿岸原産のケールなど栽培されていた野菜から、突然変異によって生まれた、あるいは近東を原産地とするものが、
ローマ帝国の衰退後にアラブ人の手によってヨーロッパに伝えられた、などと言われている。
ケールなどで開花前の蕾を食用にすることは古代から行われ、紀元前540年頃の記録にも残っている。
これは現在の食用菜の花(はなな)やカイランと同様で、今日見られるようなカリフラワーは、
この用途に適した変異種が選抜されたものと考えられる。
花蕾の断面15世紀にイタリア、フランスで栽培されはじめ、16世紀になるとヨーロッパ全体に広まり、品種改良も進んだとみられる。
18世紀頃にはインドで熱帯でも栽培できる品種が開発された。
日本では白(クリーム色)の花蕾以外ほとんど生産されていないが、オレンジ・紫等の花蕾を付ける品種もあり、カラフルである。
茎の肥大化と花蕾(からい)が発育しない性質により、花梗(かこう)は低い位置で球状の塊となる。
収穫せず生育させても、他のアブラナ属のようには伸長しない。
日本でも最近認識されてきた緑色のロマネスコ品種名「カリブロ」等も仲間である。
太い茎がミネラル・ビタミンを貯蔵する器官としての役割を果たすため、良質な花や実がつき、他のアブラナ科植物より栄養価が高い。
日本には明治初期に渡来。花梛菜(はなはぼたん)、英名カウリフラワーと紹介され試作されたが、
食用としても観賞用としても普及しなかった。
第二次世界大戦後に進駐軍向けに栽培が行われ、日本での洋食文化の広まりと、改良種の輸入、
栽培技術の進歩により昭和30年頃から広く普及した。
 byチェリー号船長の釣り日記
byチェリー号船長の釣り日記
Posted by チェリー号船頭 at 00:48│Comments(0)
│野菜・果物










 お魚おもしろ話
お魚おもしろ話