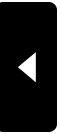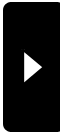2012年01月07日
人日 (じんじつ)
はやくも、1月7日です

チェリー号船頭 ベトナムにて
人日 (じんじつ) 五節句は3月3日、5月5日など奇数の月と重なる日が選ばれていますが、1月は、1日の元日を別格とし、
7日の人日を五節句(五節供)に入れています。
「七草」「七草の節句」ともいいます。
七草がゆを食べる風習は今でも残っていますね。
古代中国では、正月1日に鶏、2日に狗(犬)、3日に羊、4日に猪、5日に牛、6日に馬、7日に人、8日に穀を占う風習がありました。
その日が晴天ならば吉、雨天ならば凶の兆しであるとされていて、7日の人の日には邪気を祓うために、七草の入った粥を食べ、一年の無事を祈ったのだともいわれています。
これが日本に伝わり「七草がゆ」になりました。
平安時代は宮中の儀式でしたが、江戸時代には一般に定着し、江戸幕府の公式行事となりました。
七草がゆ
※春の七草:せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ(大根)
byチェリー号船長の釣り日記


チェリー号船頭 ベトナムにて

人日 (じんじつ) 五節句は3月3日、5月5日など奇数の月と重なる日が選ばれていますが、1月は、1日の元日を別格とし、
7日の人日を五節句(五節供)に入れています。
「七草」「七草の節句」ともいいます。
七草がゆを食べる風習は今でも残っていますね。
古代中国では、正月1日に鶏、2日に狗(犬)、3日に羊、4日に猪、5日に牛、6日に馬、7日に人、8日に穀を占う風習がありました。
その日が晴天ならば吉、雨天ならば凶の兆しであるとされていて、7日の人の日には邪気を祓うために、七草の入った粥を食べ、一年の無事を祈ったのだともいわれています。
これが日本に伝わり「七草がゆ」になりました。
平安時代は宮中の儀式でしたが、江戸時代には一般に定着し、江戸幕府の公式行事となりました。
七草がゆ
※春の七草:せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ(大根)
byチェリー号船長の釣り日記
七草(ななくさ)は、人日の節句(1月7日)の朝に、7種の野菜が入った粥を食べる風習のこと。
本来は七草と書いた場合は秋の七草を指し、小正月1月15日のものも七種と書いて「ななくさ」と読むが、
一般には7日正月のものが七草と書かれる。現代では本来的意味がわからなくなり、風習だけが形式として残ったことから、
人日の風習と小正月の風習が混ざり、1月7日に「七草粥」が食べられるようになったと考えられる。
昔の七草とは、これ以下の「春の七種(はるのななくさ)」や「秋の七種(あきのななくさ)」と異なることを指す。
米・粟・キビ・ヒエ・ゴマ・小豆・蓑米(葟・ムツオレグサ)
日本では古くから行われており、『延喜式』には餅がゆ(望がゆ)という名称で七種がゆが登場する。
餅がゆは毎年1月15日に行われ、かゆに入れていたのは米・粟・黍(きび)・稗(ひえ)・みの・胡麻・小豆の七種の穀物だった。
これを食すれば邪気を払えると考えられていた。
なお、餅がゆの由来については不明な点が多いが、『小野宮年中行事』には弘仁主水式に既に記載されていたと記され、
宇多天皇は自らが寛平年間に民間の風習を取り入れて宮中に導入したと記している(『宇多天皇宸記』寛平2年2月30日条)。
この風習は『土佐日記』・『枕草子』にも登場する。
その後、春先(旧暦の正月は現在の2月初旬ころで春先だった)に採れる野菜を入れるようになったが、その種類は諸説あり、
また、地方によっても異なっていた。現在の7種は、1362年頃に書かれた『河海抄(かかいしょう)』
(四辻善成による『源氏物語』の注釈書)の「芹、なづな、御行、はくべら、仏座、すずな、すずしろ、これぞ七種」が初見とされる
(ただし、歌の作者は不詳とされている)。
江戸時代頃には武家や庶民にも定着し、幕府では公式行事として、将軍以下全ての武士が七種がゆを食べる儀礼を行っていた。
中国にも、この日に「七種菜羹」(7種類の野菜を入れた羹(あつもの))を食べて無病を祈る習慣があった。
 byチェリー号船長の釣り日記
byチェリー号船長の釣り日記
本来は七草と書いた場合は秋の七草を指し、小正月1月15日のものも七種と書いて「ななくさ」と読むが、
一般には7日正月のものが七草と書かれる。現代では本来的意味がわからなくなり、風習だけが形式として残ったことから、
人日の風習と小正月の風習が混ざり、1月7日に「七草粥」が食べられるようになったと考えられる。
昔の七草とは、これ以下の「春の七種(はるのななくさ)」や「秋の七種(あきのななくさ)」と異なることを指す。
米・粟・キビ・ヒエ・ゴマ・小豆・蓑米(葟・ムツオレグサ)
日本では古くから行われており、『延喜式』には餅がゆ(望がゆ)という名称で七種がゆが登場する。
餅がゆは毎年1月15日に行われ、かゆに入れていたのは米・粟・黍(きび)・稗(ひえ)・みの・胡麻・小豆の七種の穀物だった。
これを食すれば邪気を払えると考えられていた。
なお、餅がゆの由来については不明な点が多いが、『小野宮年中行事』には弘仁主水式に既に記載されていたと記され、
宇多天皇は自らが寛平年間に民間の風習を取り入れて宮中に導入したと記している(『宇多天皇宸記』寛平2年2月30日条)。
この風習は『土佐日記』・『枕草子』にも登場する。
その後、春先(旧暦の正月は現在の2月初旬ころで春先だった)に採れる野菜を入れるようになったが、その種類は諸説あり、
また、地方によっても異なっていた。現在の7種は、1362年頃に書かれた『河海抄(かかいしょう)』
(四辻善成による『源氏物語』の注釈書)の「芹、なづな、御行、はくべら、仏座、すずな、すずしろ、これぞ七種」が初見とされる
(ただし、歌の作者は不詳とされている)。
江戸時代頃には武家や庶民にも定着し、幕府では公式行事として、将軍以下全ての武士が七種がゆを食べる儀礼を行っていた。
中国にも、この日に「七種菜羹」(7種類の野菜を入れた羹(あつもの))を食べて無病を祈る習慣があった。
 byチェリー号船長の釣り日記
byチェリー号船長の釣り日記
Posted by チェリー号船頭 at 00:22│Comments(2)
│船頭の知恵袋
この記事へのコメント
レイザーラモンHGみたいな写真のヤバそうな現地人は 誰なんですか?
海外では、日本語を話して近づいて来るこんな
一見やさしそうな人がめっちゃ危ないんですよね!
ストローハットは現地人なら、誰でも手編み出来るので
原価はチェリークリーニング並みに抑える事が可能ですね。
(^◇^)
海外では、日本語を話して近づいて来るこんな
一見やさしそうな人がめっちゃ危ないんですよね!
ストローハットは現地人なら、誰でも手編み出来るので
原価はチェリークリーニング並みに抑える事が可能ですね。
(^◇^)
Posted by さけおとうさん at 2012年01月07日 00:45
さけおとうさん,
褒めていただいてありがとうございます。
私も何とかベトナムで生活できそうです(笑)
褒めていただいてありがとうございます。
私も何とかベトナムで生活できそうです(笑)
Posted by チェリー号船頭 at 2012年01月07日 01:37
at 2012年01月07日 01:37
 at 2012年01月07日 01:37
at 2012年01月07日 01:37









 お魚おもしろ話
お魚おもしろ話